カウンター
カレンダー
アーカイブ
プロフィール
HN:
TWINKLING STAR
年齢:
49
HP:
性別:
男性
誕生日:
1976/01/18
職業:
普通の会社員
趣味:
最近は写真
リンク
カテゴリー
最新記事
(08/17)
(03/16)
(03/14)
(02/09)
(01/27)
(01/25)
(01/22)
(01/17)
(01/16)
(01/12)
アクセス解析
RSS
FX NEWS
-外国為替-
2025.12.03 Wed 04:19:21
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2011.02.09 Wed 06:26:45
2つくらい前にR-Mapにおけるリスクの低減を書きました。
今度はR-Mapによる事故対応判断をどうするかです。
販売前の製品安全の判断をR-Map上で行うのであれば、販売開始後の市場で起きた製品事故もR-Map上で判断しないとおかしいですもんね。
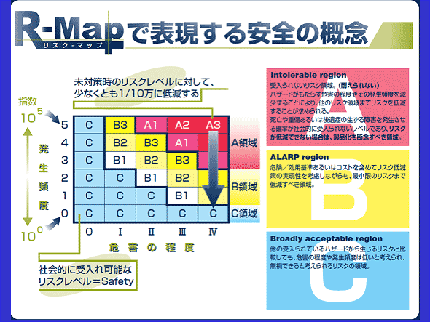
詳しくは、日科技連のサイトを御覧ください。
市場で起きた製品事故をR-Map上で判断させようとしたとき、重要なのは発生頻度ゼロレベル(最下部のC領域)をどう決めるかということ。
例えば、ゼロレベルの発生確率を「1億分の1」(10-8乗)とした場合、市場における稼働台数100万台の製品が100年間事故が起きないレベルがゼロレベルということになります。
どうやら消費生活用製品はこれくらいの頻度を設定するようです。
市場の事故情報の取扱いを簡単に言うと、
A領域:リコールすんぞ
B領域:対策すんぞ
C領域:なにもしない
って感じ。実際はこんなにスッパリ割り切れないけどね。
ゼロレベルをどう決めるか、候補は2つ。
①消費生活用製品と想定使用者が同じ(要するに不特定多数)であれば、消費生活用製品と同じ10-8乗をゼロレベルとするべき。
②自社製品の市場規模に合わせ、ゼロレベルを設定する。正直、うちの場合は10-7乗でも厳しいくらいかなと。
両方メリット・デメリットがあって、①みたいに厳しく取るとちょっとしたことで「リコールすんぞゴルァ!」ってことになるわけで。
また、②みたいに全体の流れに逆らって緩くしてしまうと結局今と変わらない判断基準(R-Map上は別に対策しなくていいけど、営業がやれって言うからやる・・・みたいな)となっちゃいそうで。
結局、システマチックにプロットすることは可能となるが、ある程度人の気持が入った上での対応判断になるかなっていう落としどころ。
製品対応はまぁコレで何とかなると思う。
もっと大変なのは「事故情報の開示と報告」。これは・・・むぅ。
↓いつもありがとうございます♪



今度はR-Mapによる事故対応判断をどうするかです。
販売前の製品安全の判断をR-Map上で行うのであれば、販売開始後の市場で起きた製品事故もR-Map上で判断しないとおかしいですもんね。
詳しくは、日科技連のサイトを御覧ください。
市場で起きた製品事故をR-Map上で判断させようとしたとき、重要なのは発生頻度ゼロレベル(最下部のC領域)をどう決めるかということ。
例えば、ゼロレベルの発生確率を「1億分の1」(10-8乗)とした場合、市場における稼働台数100万台の製品が100年間事故が起きないレベルがゼロレベルということになります。
どうやら消費生活用製品はこれくらいの頻度を設定するようです。
市場の事故情報の取扱いを簡単に言うと、
A領域:リコールすんぞ
B領域:対策すんぞ
C領域:なにもしない
って感じ。実際はこんなにスッパリ割り切れないけどね。
ゼロレベルをどう決めるか、候補は2つ。
①消費生活用製品と想定使用者が同じ(要するに不特定多数)であれば、消費生活用製品と同じ10-8乗をゼロレベルとするべき。
②自社製品の市場規模に合わせ、ゼロレベルを設定する。正直、うちの場合は10-7乗でも厳しいくらいかなと。
両方メリット・デメリットがあって、①みたいに厳しく取るとちょっとしたことで「リコールすんぞゴルァ!」ってことになるわけで。
また、②みたいに全体の流れに逆らって緩くしてしまうと結局今と変わらない判断基準(R-Map上は別に対策しなくていいけど、営業がやれって言うからやる・・・みたいな)となっちゃいそうで。
結局、システマチックにプロットすることは可能となるが、ある程度人の気持が入った上での対応判断になるかなっていう落としどころ。
製品対応はまぁコレで何とかなると思う。
もっと大変なのは「事故情報の開示と報告」。これは・・・むぅ。
↓いつもありがとうございます♪

PR
Comments
Trackbacks
TRACKBACK URL :

